
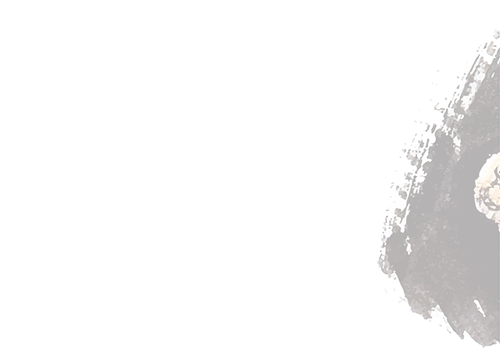
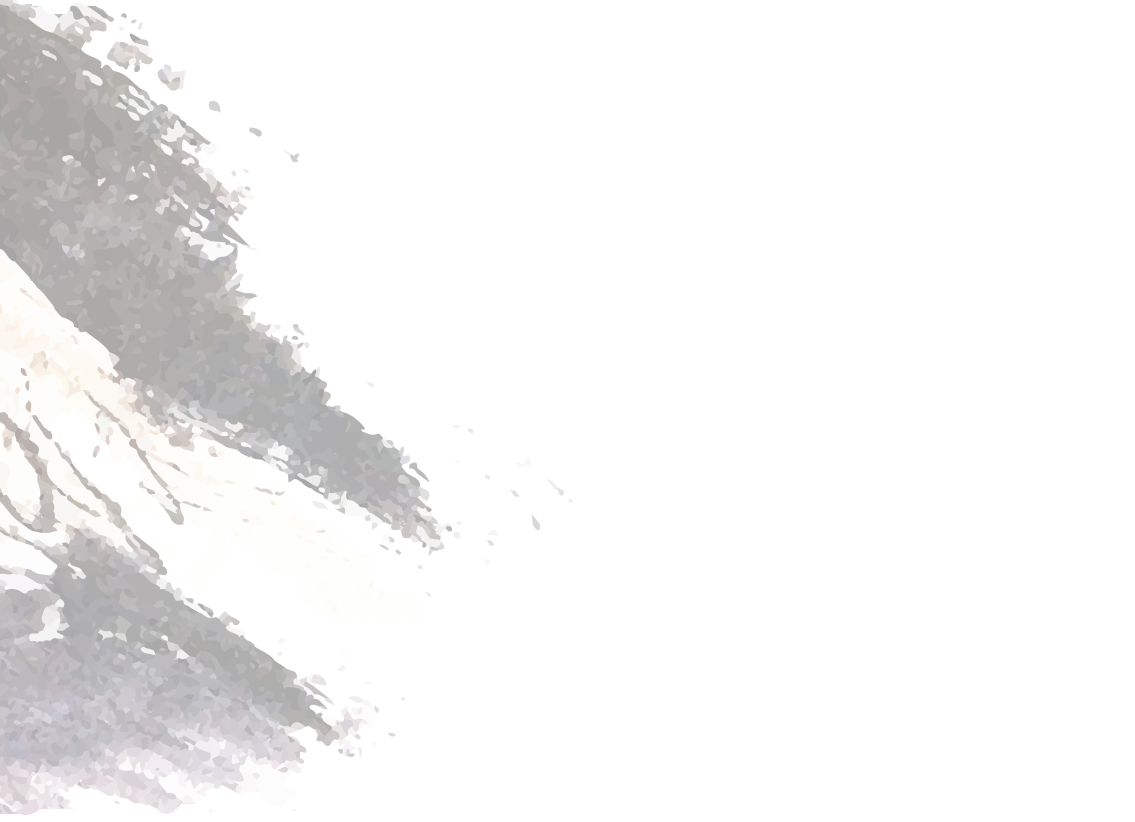
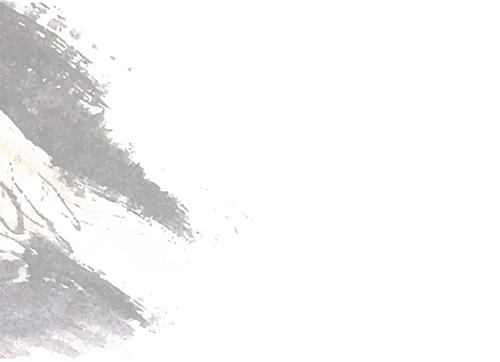


視覚文化連続講座シリーズ3
第5回「視覚文化に分け入る」
講座レポート
大野俶嵩と日本画の作家達
梶川強
(三条祇園画廊経営)
(三条祇園画廊経営)
天野一夫
(国際美術評論家連盟[AICA]会員)
(国際美術評論家連盟[AICA]会員)

日時:2023年1月14日(土曜)午後2時から3時30分
会場:京都文化博物館別館ホール
主催:きょうと視覚文化振興財団 京都新聞社
協力:平安女学院 京都新聞総合研究所
【内容】
- ●
- 新しい日本画を大野俶嵩(1922-2002)を通じて考える
【報告】
今回ご講義の梶川先生は、京都市内で画廊を経営されており、数多くの作家たちと交流されてこられました。また、天野先生は、美術館勤務を経て美術評論家として現代美術を研究されておられます。今回のご講義は、20世紀後半の日本画界で活躍した大野俶嵩について詳しく紹介されました。以下、講義内容について、お二人に報告してもらいます。(N)大野俶嵩の求めた美とギャラリーの仕事
大野俶嵩が亡くなって20年が経った。京都絵画専門学校の卒業生を中心に始めたパンリアル美術協会の設立に関わった「日本画」の革新者である。当初こそキュビスムとシュルレアリスムといった西洋の絵画思潮の中で新たな絵画をまさぐっていたが、1958年頃から麻袋(ドンゴロス)などを張り込んで、立体的に突出した物質感の高い作品に転回する。「日本画」への問いから「絵画」自体をも踏み出してしまいそうな作品だが、海外のブッリや、具体美術協会など、素材などの物質性の強調という同時代美術の流れに連動したものとも言えるが、岩絵具という物質的で触覚性の高い素材を使った「日本画」の特色を増幅したものとも言える。その後、大野は再び1970年代に描写性に回帰していく。花の写生から入りながらも、生命のかたちを描く、世界の核のような強い磁場を持つ絵画。そこでミクロコスモスはマクロコスモスに反転していく。大野は表現を大きく変化させるが一貫して<いのちのかたち>を探求した。それは定型的な形ではなく、自ら感じ、見出した<かたち>であり、本源的なものへの眼差しが常に保たれていて、その背後にある世界の理法(構造)への探求はむしろ現代の科学とも通底するものがある。 (天野一夫)
ギャラリーは作品を扱うのではなくて、作家を扱うものと考え、作家とは信頼関係で契約してきた。既存の京都の画廊では扱わない未知の新人や個性豊かな作家達をチョイスした展覧会を始めたが、その中で大野俶嵩とは1970年代初頭に出会った。大野はもともと京都の山田画廊が扱い70年代に海外の国際展にも出品し、またグッゲンハイム美術館等にも収蔵されるなど高く評価されていたが、ちょうど作品が大きく変化していた時期で、作家の「今までになかった作品を描きたい」との言葉で扱うことを決め1974年に個展を開催。
その後、1982年、銀座にアートセンターという場を作った。画廊の名を冠せずギャラリーにも貸し出すつもりだった。そこでド・スタールなどの日本では稀少な展覧会や、大野の代表作《華厳》(1987)も発表した。
2002年に亡くなるまで大野を支えてきたが、あえて一度も作品についての意見をしたことがない。作品に関しては作家が責任を持つべきで、出品作品も任せてきたのである。(梶川強)
【会場の様子】

重厚な建築内部の大ホールで開催された講義は、いつもの講座とは異なって、新鮮な雰囲気を漂わせていました。2名の先生と司会とによるディスカッションは、盛り上がっていましたが、いささか難しい内容であったと思われます。それでも理解を深めたいと考える受講生のひるむことのない熱気が伝わってきました。「しかし、それにしても難しいな。」

1988年に開館した京都文化博物館は、京都市中京区に平安建都1200年記念事業の一環として創設された博物館で、数多くの企画展覧会を通じて、京都の歴史と文化の紹介を行ってきました。別館は旧日本銀行京都支店で、明治・大正時代に活躍した辰野金吾(1854-1919)によって設計されました。通称は「ぶんぱく」で、正式名称は京都府京都文化博物館。
【連絡先】
きょうと視覚文化振興財団事務局
〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山51-35Tel / Fax:0774-45-5511