
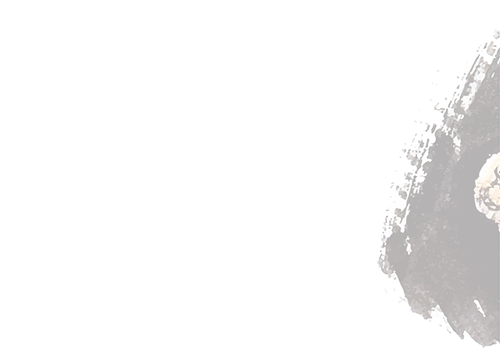
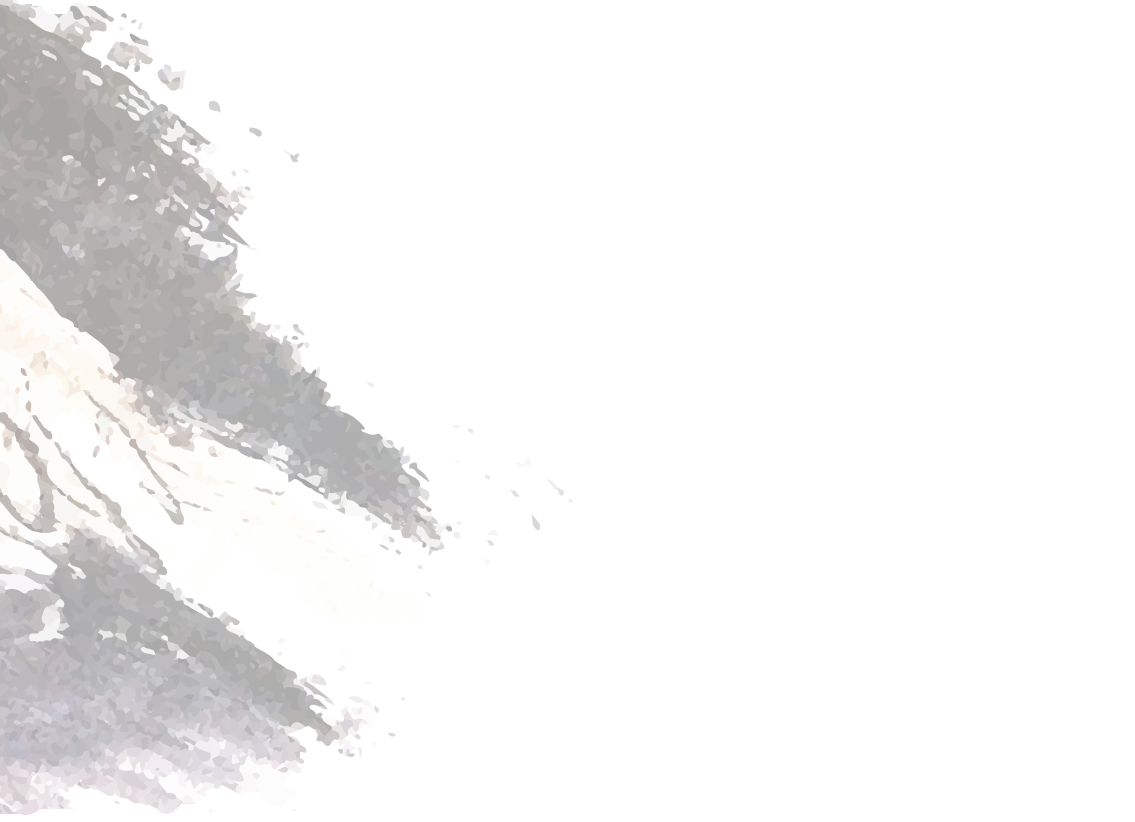
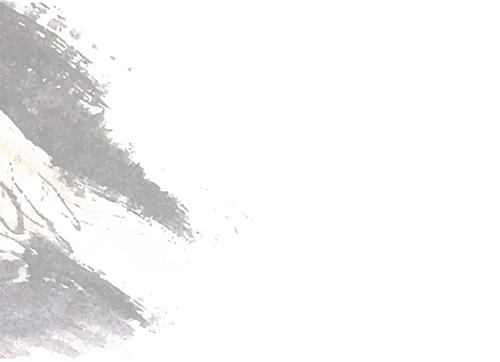


視覚文化連続講座シリーズ4
第5回「暮らしの中の視覚文化」
講座レポート
和菓子のデザイン
中山圭子
(虎屋文庫主席研究員・特別理事)
(虎屋文庫主席研究員・特別理事)

日時:2024年1月27日(土曜)午後2時から3時30分
会場:京都新聞文化センター
主催:きょうと視覚文化振興財団 京都新聞社
会場:京都新聞文化センター
主催:きょうと視覚文化振興財団 京都新聞社
【概要】
- 1. 四季折々の自然美を形に…上生菓子の原形は上菓子
- 〇上菓子とは
〇上菓子の意匠や菓銘を伝える菓子見本帳
〇上菓子の特徴
〇江戸時代を通じ、技術の向上・洗練 - 2. 菓子見本帳にみる意匠
- 〇モチーフ例
〇意匠表現 - 3. 見本帳を楽しむ
- 〇WEBで閲覧可能の見本帳が増加
- 4. 和菓子アート
- 〇和菓子にインスピレーションを受ける
- 5. NEO(ネオ)和菓子に注目
【報告】
連続講座5回目の講師は、「とらやの羊羹」で有名な和菓子メーカー虎屋の菓子資料室「虎屋文庫」――菓子に関する資料(文書や絵図、器物など)を保存・整理する機関――の主席研究員をされている中山さんです。虎屋は、もともと、室町時代後期に京都で創業し、17世紀はじめには、京都御所の近く――現在の「とらや京都一条店」――で、禁裏(御所)御用を勤めていた菓子司(現社長の黒川光晴氏は第18代当主)ですから、文庫にはたくさんの貴重な史料があるにちがいありません。中山さんのお話も、案に違わず、菓子見本帳――富裕な顧客が上菓子を注文するときに利用した商品カタログ――などの珍しい資料を駆使したもので、近世の都人が菓子に寄せた思いと、中山さんの菓子への愛を覗わせるのに十分なものでした。「上菓子」とは、当日、配付された資料によると、「現在の上生菓子の原形ともいえる上菓子(白砂糖を使った上等な菓子)」のことで、「花鳥風月にちなむ菓銘や意匠をもつものが中心で、17世紀後半、京都を中心に作られ、広まった。富裕層を顧客とし、行事や儀礼、冠婚葬祭などの贈り物ほか、茶会の菓子として使われた」とのことです。中山さんは、菓子見本帳をスライドで映しながら、描かれた菓子のひとつひとつについて、丁寧に、四季折々の風物をモチーフとする意匠(design)や古典文学に由来する菓銘(name)、さらには、材料や製法を説明されました。その目的は、菓子が「五感の芸術」であることを示すために他なりません。というのも、見本帳に描かれた菓子の意匠が視覚に関係していることは言うまでもありませんが、材料と製法は、私たちが、菓子を食べたときに感じるはずの咀嚼音(聴覚)や香り(嗅覚)、味わい(味覚)、舌触りや手触り(触覚)といったものを想像するのに必要な情報だからです。もっとも、菓銘の位置づけは微妙です。たしかに、菓銘は言葉である以上、音声として、聴覚に訴える側面はあります。たとえ実際に発声されない場合でも、言語記号として機能するためには、音声(音素)的に分節される必要があります。しかし、だからといって、菓子を食べたときの咀嚼音と、菓銘の音声的側面とを同列に論じるのは、ちょっと違和感があります。というのも、菓銘にとって重要なのは、感覚的な音声そのものというよりは、音声によって伝達される「意味」という概念的あるいは心的なものだと考えられるからです。

霜紅梅
このことは、私たちが、「五感の芸術」としての菓子のあり方に、意味の観点からアプローチすることを勧めているように思われます。というのも、菓銘に当てはまることは、意匠にも当てはまるからです。意匠はたしかに、視覚に訴えます。しかし、意匠は、ひとつの視覚記号として、意味を伝達します。例えば、今回、中山さんの身代わりとなったお菓子を取り上げてみましょう。仮に、誰かが「この菓子は何に見えますか」と質問されたとしましょう。菓子を作った人が「梅の花」として作ったとするなら、「梅の花に見えます」と答えるのが正解ということになりますが、さて、どれほどの人が正解を答えることができるでしょうか。中には「桃の花に見えます」とか「桜の花に見えます」とかと答える人もいるでしょうし、「わかりません」と答える人もいて、そのような人たちは「あなたは誤解している」とか「あなたは花を知らない」とかと言われるにちがいありません。ただし、その際、最も重要なことは、「この菓子は何に見えますか」と問われて、「紅色の球体が5つくっついているのが見えます」と言う人はいないということなのです。要するに、ものを「見る」ことは、単に視覚的な感覚を得ることではなく、「何かとして見る」ことであり、「何かとして見る」ことは、常にして既に、その何かについての知識を前提しているということなのです。すなわち、誰かが、この菓子を「梅として見る」ためには、その誰かは「梅」が「桃(花びらの先がやや尖っている)」や「桜(花びらの先が割れている)」とは異なって、「花びらの先が丸い」ということを知っている必要があるのです。言い換えれば、「知らないもの」は「見えない」のです。
このことが正しいとすると、菓銘は、菓子を「見る」ということに重要な役割を果たしていることは、すぐさま理解されるはずです。なぜなら、菓銘は、その概念的あるいは心的な意味によって、「見ること」を可能にするからです。例の菓子を目の前にして、「紅梅」という菓銘を与えられれば、多くの人は、たとえ花弁の形を知らない人でも、「紅梅として見る」ことができるはずです。もっとも、それで十分というわけではありません。この菓銘は「霜紅梅」であって、虎屋のHPには、「霜紅梅」の説明として「うっすらと霜が降りた梅の花を思わせます」と記されています。菓銘を聞かなくても、この菓子を「紅梅として見る」ことのできる人がいるかもしれませんが、白いぶつぶつを「霜として見る」ことはなかなか難易度が高いように思われます。したがって、この菓子に対面したとき、同時に「霜紅梅」という菓銘を知らされてはじめて、多くの人たちは、この菓子を、厳しい寒さの中で春を告げ、春の喜びを表す花として見ることができ、そのようなものとして、五感を動員して菓子を味わうことができるように思うのです。
菓銘は、したがって、五つの感覚と直接的に結びついているというよりは、視覚を補強する心的な情報を提供するものとみなすのがよいように思われます。いずれにしても、人が美味しいと感じることの80%は視覚と情報に依存しているようですので、菓子にとって、意匠と菓銘は、そのアイデンティティーを保証する重要なものであることに変わりはありません。中山さんが配布された「虎屋文庫50周年記念!和菓子の〈はじめて〉物語展」と題された小冊子(2023年10月刊)によれば、このような意匠と菓銘を特徴とする上菓子の誕生には、後水尾天皇(1596~1680)を中心とした文化人たちの交流が影響しているとのこと。「宮中で催された古典文学や和漢の連歌、立花や茶の湯の会などには、宮中以外からも僧侶や絵師ほか、さまざまな人々が集った。そこで共有された教養や美意識は、菓銘や意匠の創出に影響を与え、やがて上菓子の誕生につながっていったのだろう」と記されています。いやはや、これは大変なことになりました。ひとつの上菓子を味わうためには、江戸時代の京都に生きていた知識人たちと「教養や美意識」を共有する必要があるということですから、生半可な知識と未開発の感性しか身につけていない現代人には、かなりハードルの高いことにちがいないからです。(K)
このことが正しいとすると、菓銘は、菓子を「見る」ということに重要な役割を果たしていることは、すぐさま理解されるはずです。なぜなら、菓銘は、その概念的あるいは心的な意味によって、「見ること」を可能にするからです。例の菓子を目の前にして、「紅梅」という菓銘を与えられれば、多くの人は、たとえ花弁の形を知らない人でも、「紅梅として見る」ことができるはずです。もっとも、それで十分というわけではありません。この菓銘は「霜紅梅」であって、虎屋のHPには、「霜紅梅」の説明として「うっすらと霜が降りた梅の花を思わせます」と記されています。菓銘を聞かなくても、この菓子を「紅梅として見る」ことのできる人がいるかもしれませんが、白いぶつぶつを「霜として見る」ことはなかなか難易度が高いように思われます。したがって、この菓子に対面したとき、同時に「霜紅梅」という菓銘を知らされてはじめて、多くの人たちは、この菓子を、厳しい寒さの中で春を告げ、春の喜びを表す花として見ることができ、そのようなものとして、五感を動員して菓子を味わうことができるように思うのです。
菓銘は、したがって、五つの感覚と直接的に結びついているというよりは、視覚を補強する心的な情報を提供するものとみなすのがよいように思われます。いずれにしても、人が美味しいと感じることの80%は視覚と情報に依存しているようですので、菓子にとって、意匠と菓銘は、そのアイデンティティーを保証する重要なものであることに変わりはありません。中山さんが配布された「虎屋文庫50周年記念!和菓子の〈はじめて〉物語展」と題された小冊子(2023年10月刊)によれば、このような意匠と菓銘を特徴とする上菓子の誕生には、後水尾天皇(1596~1680)を中心とした文化人たちの交流が影響しているとのこと。「宮中で催された古典文学や和漢の連歌、立花や茶の湯の会などには、宮中以外からも僧侶や絵師ほか、さまざまな人々が集った。そこで共有された教養や美意識は、菓銘や意匠の創出に影響を与え、やがて上菓子の誕生につながっていったのだろう」と記されています。いやはや、これは大変なことになりました。ひとつの上菓子を味わうためには、江戸時代の京都に生きていた知識人たちと「教養や美意識」を共有する必要があるということですから、生半可な知識と未開発の感性しか身につけていない現代人には、かなりハードルの高いことにちがいないからです。(K)
【会場の様子】

今回も、会場は京都新聞本社の7階にある京都新聞文化ホール。相当に広いホールなのですが、さすがに60名以上の方々が参加されると、ぎっしりという感じになります。テーマが和菓子ということもあって、皆さん、興味深くお話を聞いておられました。なお、今回は、皆さんお楽しみの抽選会はありませんでした。その代わり、出席された方々全員に、西宮市大谷記念美術館で、3月2日~4月21日の間開催される予定の「生誕130年・没後60年を越えて/須田国太郎の芸術――三つのまなざし 絵画・スペイン・能狂言」展の招待券がプレゼントされました。開催館のご厚意に感謝します。
【連絡先】
きょうと視覚文化振興財団事務局
住所 : 〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232