
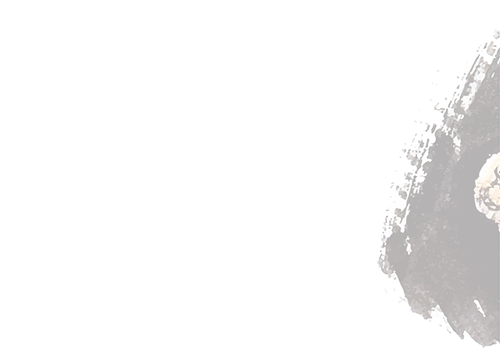
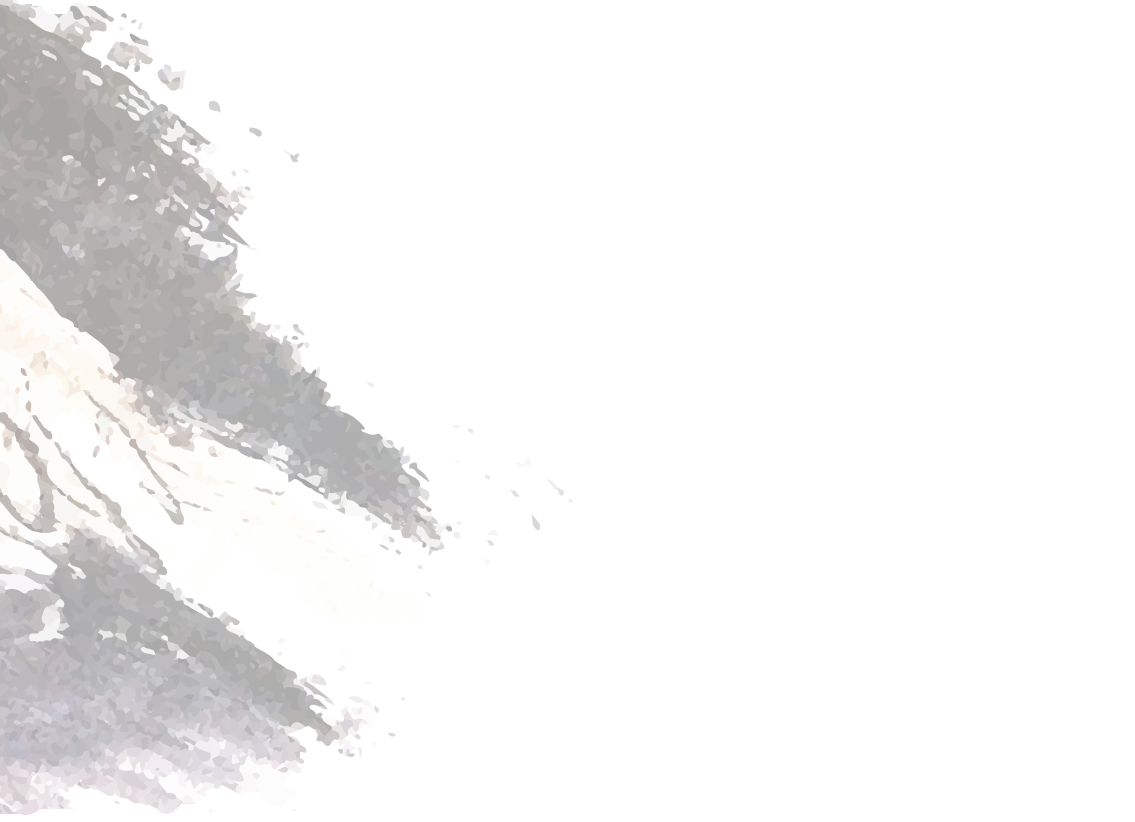
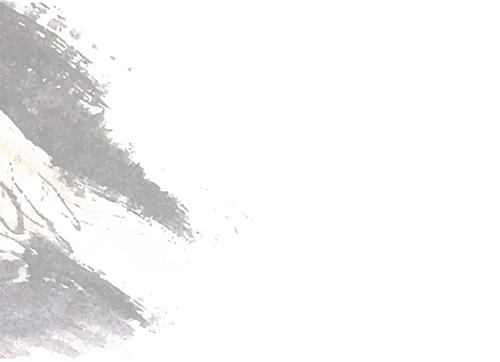


視覚文化連続講座シリーズ5
第1回「視覚文化の不易流行」
講座レポート
匂いを見る・香りを聞く
~香道から
濱崎加奈子
(京都府立大学准教授((公財)有斐斎弘道館館長))
(京都府立大学准教授((公財)有斐斎弘道館館長))

日時:2024年9月21日(土曜)午後2時から3時30分
会場:同志社大学今出川校地寧静館N21教室
主催:きょうと視覚文化振興財団
会場:同志社大学今出川校地寧静館N21教室
主催:きょうと視覚文化振興財団
【内容】
- ○ 和歌にみる匂い・香り
- ○ 源氏物語と匂い・香り
- ○ 香木と銘
- ○ 伝統文化プロデュースの現場から
【報告】
今年度の視覚文化連続講座がようやく始まりました。今年はシリーズ5となり、全体のタイトルは「視覚文化の不易流行」です。第1回講座の講師にお招きしたのは、京都府立大学准教授で(公財)有斐斎弘道館館長でもいらっしゃる濱崎加奈子さんです。
濱崎さんのお話のメインテーマは「香道」ですが、その前に濱崎さんが携わっておられる、京都の伝統文化の再興イベントをプロデュースする活動が紹介されました。
例えば、室町時代に将軍足利義政の前で行われた「糺河原勧進猿楽」の再興を目指す下鴨神社舞殿での「糺勧進能」の上演、あるいは北野天満宮で千百余年ぶりに「曲水の宴」を催す再興プロデュースなどです。私は、両方ともにその存在を知りませんでしたので、京都の文化の厚みと奥深さに改めて思いを致すことになりました。
さて、濱崎さんは東京大学大学院総合文化研究科に提出された博士論文で「匂い/香り」について研究成果を披露され、それを『においの美学』(思文閣出版 2017年)という書物に纏められました。今回は、その「匂い/香り」についての講演をお願いしました。
最初に「匂い」と「香り」という言葉の違い、二つの言葉に対する私たちの受け止め方の違いについてのお話がありました。現代の私たちは、確かに「匂い」にはややマイナスのイメージを持っています。つまり「匂い」=「悪臭」というイメージです。それに対して「香り」という語については良いイメージ、上品で好ましい匂い、つまり芳香という感覚を持っています。しかし、元来「匂い」は、広辞苑に「赤などのあざやかな色が美しく映えること」とあるように、好ましい色・艶などを表す言葉であることを私たちは知っています。「匂い立つような美しさ」のようにも使う言葉ですね。それに対して、不快な悪い匂いは「臭(におい)」と表記し、「臭い(くさい)」と表すのが普通のようです。
今日の本題の「匂いを見る・香りを聞く~香道から」は、日本の歴史の中で「匂い・香り」、すなわちここでいう「よい香り/芳香」がどのように受容されてきたのかを過去の文献史料の中に求めて、「匂い・香り」の文化の様相を通覧することが中心テーマであったと思います。
史料として『日本書紀』垂仁天皇条の「非時香菓(ときじくのかくのみ)」―これは橘の実だそうです―という記述、同じく『日本書紀』推古天皇条の「香木伝来」の話、万葉集の和歌に謳われた桃や梅の「にほひ」や「香」、そして『源氏物語』に描かれている香りが紹介されました。すなわち、日本では古より「匂い・香り」に関心がもたれ、それが次第に一種の文化つまり香道にまで昇華されていく過程が資料によって示されたことになります。
私は、『源氏物語』「若紫」帖の三つの香り―「そらだきもの」(空間全体に広がる香り)、「名香の香」(仏前の線香の香り)、「御追風」(光源氏の着物に炷【た】き込められた香り)―が交錯する描写にいたく感心しました。視線の交錯や音の交錯は比較的容易にイメージできますが、匂い・香りの交錯の様はとても新鮮です。昔、国文学の先生に「『源氏物語』は油断も隙もない」という話しを聞いたことがあります。三つの香りが交錯する様子をさりげなく表現し、匂い/香りが複雑に広がっていく空間をイメージさせるところにも、紫式部の「油断も隙もない」筆力が現れていることになるのだろうと思いました。
紫式部の表現力の卓抜さの話になってしまいましたが、少なくとも11世紀初めの平安時代に、「匂い/香り」を文化にまで高めた社会がすでにあったことを『源氏物語』は示していることになります。
香道に関する資料は、茶道や華道に比べるとずいぶん少ないようですが、現在に伝わる香道の源は15~16世紀に志野宗信や三條西実隆といった人にあるということでした。それを背後で支えていたのは足利義政が推進した東山文化であったようです。室町時代から後世に伝え遺された数々の文化について、足利義政という人が果たした役割を再認識しました。
最後に「組香」の説明がありました。今日、香道という場合に私たちがまず連想するのは、「組香」だと思います。香炉を持ち片方の手でそれを覆い、厳かな様子で香を「聞く」姿は、時折テレビにも映し出されます。「組香」は、それぞれ固有の銘を持つ何種類かの香木を炷き、それを聞き分けて何の香木であるのかを当てて鑑賞する遊戯ですが、どこかで見たことのあるあの線の組み合わせの記号の意味がやっと分かりました。あの記号は回答であって、三つの香の場合、それぞれの答えの意味は次のようになります。なお、それぞれの記号は、縦書きの手紙と同じように、右から左に読みます。

A:三つとも同じ。B:最初は別で、あとの二つは同じ。 C:最初と最後が同じで、二番目は別。D:最初の二つは同じで、最後は別。E:三つとも別。
香の数が五つに増えると回答の可能性は一気に52種類に増えます。この52の回答に『源氏物語』全54帖から最初の「桐壺」と最後の「夢浮橋」を除いた52帖の名前を付けた「組香」を「源氏香」と呼ぶのだそうです。雅の世界です。
何年か前にアラン・コルバンという人の『においの歴史 嗅覚と社会的想像力』という本を読んだことがあります。原書はフランス語で『瘴気と黄水仙 嗅覚と18-19世紀の社会的想像力』が原題の訳です。「瘴気」というのは病気を引き起こす悪い空気で、「黄水仙」はここでは新しい香水の原料を意味しています。つまり、この書はパリを中心とする当時のフランス社会に充満していた「臭い匂い」を社会の象徴(貧民の悪臭、排泄物、腐敗臭等々)として捉え、エリートたちが黄水仙から生成される香水へと逃避していく事情を、これも象徴的に語っています。すなわち19世紀にいたるまでヨーロッパでは嗅覚は軽蔑される低級な感覚であり、臭は忌み嫌われていたわけです。もちろん、日本でも近世に至るまでは町には排泄物などの悪臭があったにちがいありません。《餓鬼草子》(《紙本著色餓鬼草紙》第3段「食糞餓鬼図」)を見ると、人々が道端で用を足した糞を餓鬼が食べようと狙っている様子が描かれており、町に悪臭が漂っていた有様が推測されます。
しかし、一方で今日の講演を通して、日本では平安時代以前から、貴族社会で「匂い/香り」を一種の文化、芸道にまで高める兆しが育まれてきたことを知ることができました。それが最近では市民社会にまで浸透しています。実は、我家のトイレ消臭剤はスプレー式の消臭剤ではなく、なんとひと箱40本入り1000円の「沈香」(もちろん上等なものではないでしょうが)なのです。娘の趣味なのですが、いちいち火をつけて炷く必要があるので面倒とはいうものの、人工臭とは違う趣はありますかねぇ。最後に「臭」の中の「匂」となったところで、レポートを終わりとさせていただきます。(I)
【会場の様子】

今年度から同志社大学今出川校地寧静館N21教室をお借りして、この連続講座を開催することになりました。地下鉄烏丸線今出川駅の北側改札口を出ると同志社大学のキャンパスに直通するエレベーターがあります。エレベーターで昇って降りると、そこはもう同志社大学の良心館という建物の中です。大きな学生食堂もありますから、気軽にご利用ください。コンビニもあります(今回は、大学がまだ夏季休暇中で食堂、コンビニともに閉まっていました。申し訳ありませんでした)。
会場の寧静館N21教室までは少し迷われるかもしれません。学生食堂の前を通って、階段かエレベーターで1階に上ります。1階に着いて西に向かって直進すると良心館から出られます。その後、右に曲がって寧静館の入口までお進み下さい。入口に案内板がありますから、エレベーターで2階会場までお越しください。
会場の寧静館N21教室までは少し迷われるかもしれません。学生食堂の前を通って、階段かエレベーターで1階に上ります。1階に着いて西に向かって直進すると良心館から出られます。その後、右に曲がって寧静館の入口までお進み下さい。入口に案内板がありますから、エレベーターで2階会場までお越しください。
【連絡先】
きょうと視覚文化振興財団事務局
〒607-8154 京都市山科区東野門口町13-1-329電話 : 075-748-8232