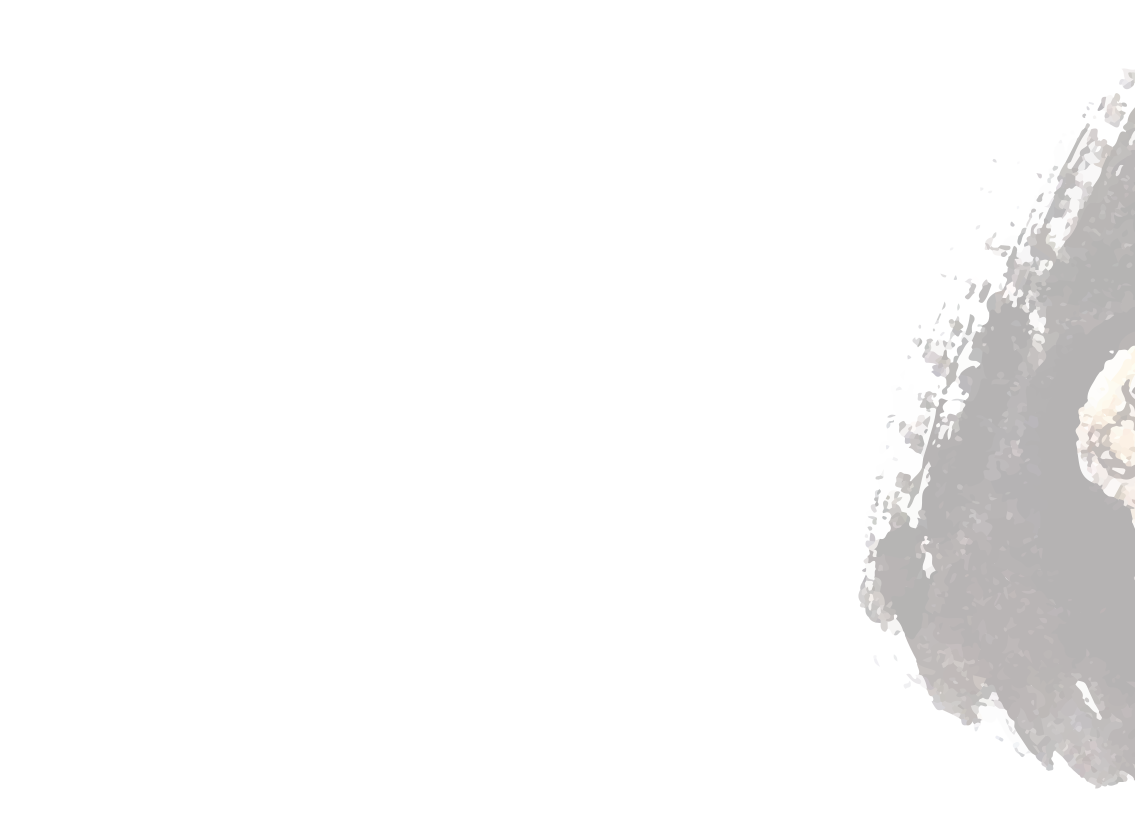

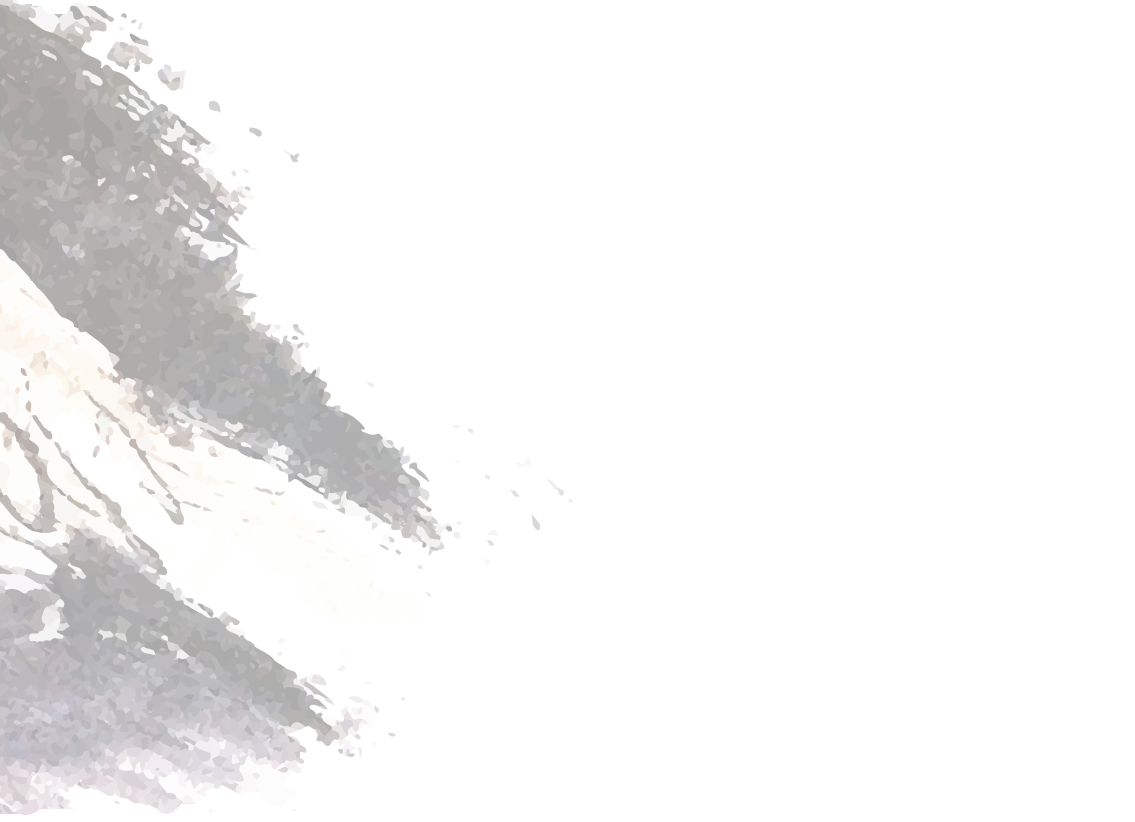
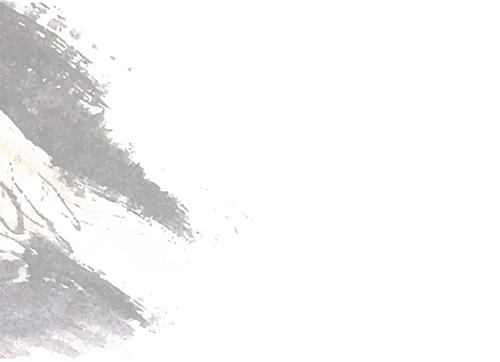


視覚文化連続講座シリーズⅠ 第6回「視覚の文化地図」講座レポート
視覚に訴える鉄道のイメージアップ策
-これまでの取組み・現状・今後-
須田寛
(JR東海相談役)
(JR東海相談役)

日時:2021年6月19日(土曜)午後2時から3時30分
会場:平安女学院大学京都キャンパス
主催:きょうと視覚文化振興財団 京都新聞社
協力:平安女学院 京都新聞総合研究所
視覚文化連続講座シリーズⅠの第6回は、コロナ禍のため、延期されていましたが、ようやく開講の運びとなりました。今回も、あいにくの雨。平安女学院のファザードが、雨にぬれながら、受講者を出迎えていました。
須田さんは1931年生まれで、今年が2021年ですから、ちょうど90歳になられました。6月末をもって、JR相談役を退かれるとのこと。長年のお努め、お疲れさまでした。それにしても、お元気です。お話しのスイッチが入ると、立て板に水どころではありません。面白いお話しが、次から次へと溢れ出てきて、まるで尽きることのない泉のようです。しかも、その面白さは、須田さんが、JRという運輸サービスを担う巨大企業で身をもって体験されたことの裏付けがありますから、思わず引き込まれてしまいます。いやいや、この言い方は正確ではありません。その圧倒的な水量に思わず溺れてしまいそうになります。
今回のお話しは、須田さんが関与されたさまざまな「JRのイメージアップ策」についてでした。具体的に言えば、駅頭掲示板(駅の改札口付近などに設置される伝言板)やポスター、切符、列車行先標(列車の行先を表示するために列車の側面などに設置されるサインボード)、駅名標(駅名の表示板)など、私たちに馴染みのものに施されたさまざまな視覚的な工夫についてです。「視覚文化」という私たちにとって身近な「芸術現象」に関心を寄せる弊財団の講座にふさわしいテーマと言えるでしょう。
お話しは、具体的な事例を、配布資料とスクリーンに投影された映像で示しながら、視覚的な「工夫」を指摘し、その効果について説明するという形で進められました。ひとつひとつの工夫と、その効果は、興味深いものでしたが、最も興味深かったのは、工夫の直接的な効果というよりも、ある視覚的な工夫が、企業の内外に及ぼすさまざまな間接的・波及的な効果です。例えば、駅の掲示板を「見やすく」すると、乗客が助かるばかりか、駅員への質問が減る分、駅員が助かって、そのエネルギーが他のサービスに向けられ、結果的に、JR全体のイメージアップに繋がるというようなことで、さすがに、このような作用連関は、企業の活動を巨視的・全体的に眺める経営者としての視点がなければ、語りえないものにちがいありません。
お話しの最後は、旅行者が関与している2つの世界、すなわち、現実世界とデジタル世界との間を、どのようにデザイン的に折り合わせるかという問題に関する「今後の展開」で締めくくられました。今後、機会があれば、視覚文化をを見る企業経営者の「眼」について、もっと詳しくお話ししてもらいたいと痛切に感じています。
【要旨】
私の現場実習時、駅長・駅職員の協力で、標記の社会実験を行い、一定の効果をおさめた。古い記録であるが、視覚に訴えて、従来(現代)の常識と異なる方向からイメージアップ、サービス向上がはかられた事例を紹介したい。
【目次と内容】
須田さんは1931年生まれで、今年が2021年ですから、ちょうど90歳になられました。6月末をもって、JR相談役を退かれるとのこと。長年のお努め、お疲れさまでした。それにしても、お元気です。お話しのスイッチが入ると、立て板に水どころではありません。面白いお話しが、次から次へと溢れ出てきて、まるで尽きることのない泉のようです。しかも、その面白さは、須田さんが、JRという運輸サービスを担う巨大企業で身をもって体験されたことの裏付けがありますから、思わず引き込まれてしまいます。いやいや、この言い方は正確ではありません。その圧倒的な水量に思わず溺れてしまいそうになります。
今回のお話しは、須田さんが関与されたさまざまな「JRのイメージアップ策」についてでした。具体的に言えば、駅頭掲示板(駅の改札口付近などに設置される伝言板)やポスター、切符、列車行先標(列車の行先を表示するために列車の側面などに設置されるサインボード)、駅名標(駅名の表示板)など、私たちに馴染みのものに施されたさまざまな視覚的な工夫についてです。「視覚文化」という私たちにとって身近な「芸術現象」に関心を寄せる弊財団の講座にふさわしいテーマと言えるでしょう。
お話しは、具体的な事例を、配布資料とスクリーンに投影された映像で示しながら、視覚的な「工夫」を指摘し、その効果について説明するという形で進められました。ひとつひとつの工夫と、その効果は、興味深いものでしたが、最も興味深かったのは、工夫の直接的な効果というよりも、ある視覚的な工夫が、企業の内外に及ぼすさまざまな間接的・波及的な効果です。例えば、駅の掲示板を「見やすく」すると、乗客が助かるばかりか、駅員への質問が減る分、駅員が助かって、そのエネルギーが他のサービスに向けられ、結果的に、JR全体のイメージアップに繋がるというようなことで、さすがに、このような作用連関は、企業の活動を巨視的・全体的に眺める経営者としての視点がなければ、語りえないものにちがいありません。
お話しの最後は、旅行者が関与している2つの世界、すなわち、現実世界とデジタル世界との間を、どのようにデザイン的に折り合わせるかという問題に関する「今後の展開」で締めくくられました。今後、機会があれば、視覚文化をを見る企業経営者の「眼」について、もっと詳しくお話ししてもらいたいと痛切に感じています。
【要旨】
私の現場実習時、駅長・駅職員の協力で、標記の社会実験を行い、一定の効果をおさめた。古い記録であるが、視覚に訴えて、従来(現代)の常識と異なる方向からイメージアップ、サービス向上がはかられた事例を紹介したい。
【目次と内容】
- (1)
- 視覚に訴えてフロントサービスの改善
駅頭掲示などをより強く視覚に訴えるため、デザイン字体等を改善した。これにより、乗客も鉄道職員に説明を求めることなく、自らの判断で鉄道を自由に利用できるので、最終的にフロントサービスの改善につながる。同時に企業としての鉄道のイメージアップとなる(読む掲示から見る掲示へ) - (2)
- 視覚に訴えて不正乗車の防止
不正乗車による逸失収入は年数百億円にのぼるとみられていた。この防止は50年代(昭和)の産業課題となっていた。不正乗車防止を大キャンペーンとして実施、そのポスター作成からきっぷのデザイン変更まで徹底した視覚に訴えるキャンペーンとした(このキャンペーンはオレンジを基調色として展開)。 - (3)
- 視覚に訴えて旅心をいざない乗客増をはかる
旅心を高めた段階で、旅行誘致にかかわる新しいサービス、商品を次々と展開。これを受け皿として一気に乗客増に結び付ける。 - (4)
- 視覚に訴えて旅行を円滑に
乗客が旅行に際してまず注目するものは列車行先標、駅名標等である。これらのデザインを一新、より見やすい判りやすいものとして円滑な旅行を実現する。 - (5)
- 今後の展開
IT技術の急進に伴い、視覚に訴える乗客への諸情報も携帯端末で顧客が乗車前に、また乗車時に随時把握できる状況となった。従って、顧客端末から出力される諸情報を体系化する情報のシステム化とそのデザインが求められる状況となっている。しかし、顧客とくに観光客の場合、目的地ないしはそこに至る過程を実視して味わうものである以上、前述のような掲示案内標の必要性はこれからも残るものと思われる。従って、端末から出力される情報と現実の情報提供両者のそれぞれのデザインに総合性(整合性)が求められる。
【会場の様子】

須田さんは、1時間30分にわたって、立ちっぱなし。パソコン操作係は、座っていますので、皆さんから、敬老精神が足りないとお叱りを受けそうです。しかし、これが須田さんの講演スタイル。立たないと元気が出ない、ということで、イスをお勧めしたのですが、お断りになられました。長身痩躯。飄々としておられるように見えますが、お話しには熱意が込められ、空間的・時間的な状況への配慮は、実に細やかで、行き届いていらっしゃいました。

雨の中、たくさんの受講者に来ていただき感謝します。「三密」を避けることが、現在の最重要課題です。ご協力いただいている平安女学院の方々や、京都新聞の方々にも感謝です。ちなみに、正面のスクリーンの映されているのが、「ディスカバー・ジャパン」のポスターです。実は、あまり大きな声では言えないのですが、ポスターの縦横の比率が、実物とは、若干異なっています。縦長に映っているのです。分かってはいたのですが、比率を適正化するパソコンの操作の仕方が分からず、そのままになっています。「視覚文化」について議論するときに、このようなことではいけません。お詫びするとともに、パソコンの操作に習熟することをお約束します。

地域毎に色分けされた「スマート」な列車行先標を持って、受講者にお見せする入江事務局長。ただし、この行先標はミニチュアで、須田さんが、デザイン変更の記念に贈られたものを、持参されました。入江さんには、財団の事務長として、講座の運営に、なにかとご尽力いただいています。この場を借りて、お礼申し上げます。
【連絡先】
きょうと視覚文化振興財団事務局
〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山51-35TEL / FAX 0774-45-5511
Mail / info@kyoto-shikakubunka.com