
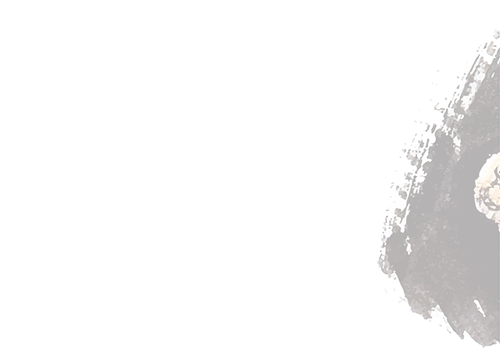
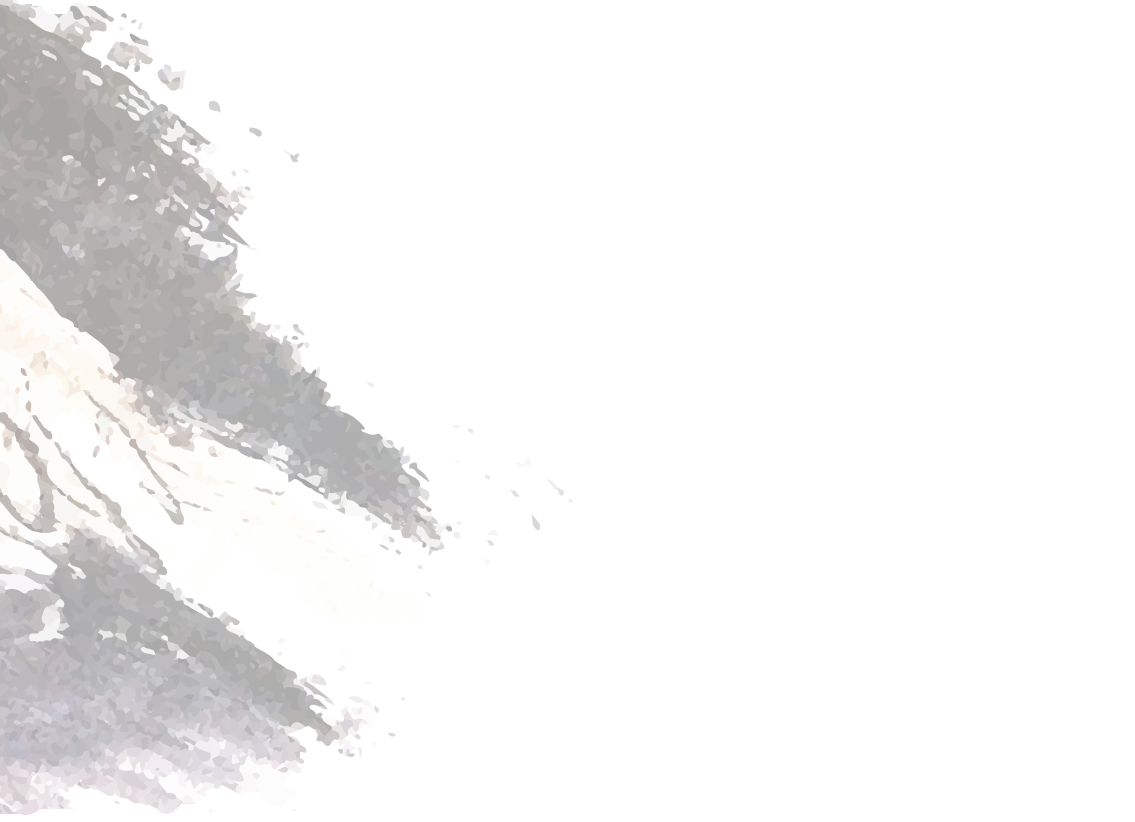
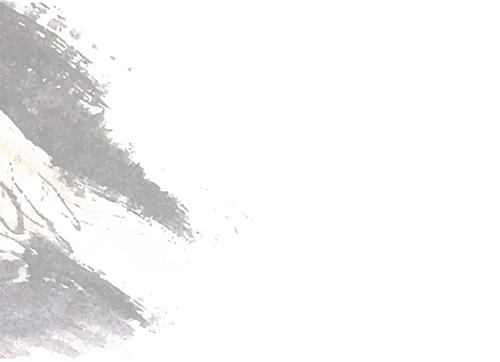


2023年度 第4回 視覚文化公開ワークショップが開催されました
2023年度第4回目の視覚文化公開ワークショップが、2024年1月28日(日) 午後2時から4時30分頃まで、同志社大学今出川校地至誠館S2教室で、対面とZOOMのハイブリッド形式で行われました。会場には、今回のゲストである堤拓也さん(インディペンデント・キュレーター、グラフィックデザイナー)と、コーディネーターである渡辺亜由美研究員をはじめ、天野和夫、佐藤守弘、杉山卓史、はがみちこ研究員が全員集合しました。財団からは、岸文和理事が来場しましたが、岩城見一理事長と中谷伸生理事はズーム参加。中谷理事は、昨年9月にコロナに罹られて3ヶ月の長きにわたって生死の境を彷徨われましたが、幸いなことに生還されました。まだ味覚障害が残っているとのことで、無理は禁物です。なお、Zoomで、何人かの方が参加されました。嬉しい限りです。今後とも、奮って参加していただくようお願いします。

堤拓也さんと渡辺亜由美研究員
今回は、渡辺亜由美研究員の担当です。渡辺さんは、現在、京都国立近代美術館で特定研究員をされていますから、美術館での「展示」について、問題意識をお持ちなのはきわめて自然なこと。今回は、インディペンデント・キュレーターとして幅広く活躍されている堤拓也さんをゲストにお迎えして、「展示室の外側」というテーマでプレゼンが行われ、その後は、来場者も積極的に参加して、活発な議論が行われました。「展示室」というと、すぐさま念頭に浮かぶのが、1929年に開館したニューヨーク近代美術館(MoMA)が導入した「ホワイトキューブ」。その白く塗られた壁面によって囲われ、均質な光に満たされた空間は、近代美術の純粋性や自律性を物理的・象徴的に担保する展示空間でした。今回のワークショップは、この展示室の外側で、今、起こっていることについての堤さんのご報告を踏まえて、「展示」という行為――キュレーターが、何らかのコンセプトに基づいて、収集・選択した複数の作品を、時間的・空間的な関係を考慮しながら、特定のコンテクストにおいて、結合・配置すること――に焦点を合わせて考えようとするものです。では、渡辺さんと堤さんに報告をお願いするにしましょう。(K)
【趣旨】
美術館の「展示室」は、とても不自然な場所です。たくさんの「注意事項」(~してはいけません)、無機質な白い壁、話し声や時に足音さえ注意される静かな空間。温湿度は年間を通じてほぼ均一に保たれているため、夏場は肌寒く感じるかもしれません。しかしこうした不自然さは、作品を守り、適切な環境で展示するために不可欠なものです。そして「適切」という言葉の中には、作品を物理的に守るための「適切」という意味に加え、作品の自律性を担保するモダニズム的な制度を正当化する上で「適切」である、という意味合いが今なお込められています。
この適切さ、あるいは権威をめぐり、展示室の内側・外側で行われた数多くの批評的な表現活動は、そのまま美術を巡る歴史でもあります。
今回ゲストにお招きするキュレーター/デザイナーの堤拓也さんはこれまで、展示室の「外」での仕事も数多く手がけてきました。その実践は、短絡的な地域振興型の取り組みとは明確に一線を画すものです。作品・場・鑑賞者の関係を動的に捉え、展覧会という形式の組み直し/読み直しを試みる堤さんのこれまでのお仕事について伺いながら、展示室という不自然な場所の外、あるいは中で起こるさまざまな事象について考えてみたいと思います。

堤拓也さん
【報告】
第4回ワークショップでは、まずコーディネーターの渡辺から「展示室の外側」というテーマ背景について話をした。1960年代のドナルド・ジャッドによる美術館とキュレーター批判の事例を出発点に 、ホワイトキューブ制度と文化財を守り管理する機能や運営とがぶつかる日本の美術館独特の状況を指摘した後、展示室の外側での活動例として日本型アート・プロジェクト/地域アートの特徴や論点を簡単に整理した。その後ゲストスピーカーの堤拓也さんにバトンタッチし、前半は仕事の背骨となる理論や影響を受けた人物、ポーランドでの留学経験について、後半は堤さんが企画・運営に関わった2020年以降の仕事の中から、展示室の外側で開催した展覧会についてお話をいただいた。
発表全体を通じて興味深かった点は、西洋主体の博物館学や美術史、展示制度を踏まえながら、大きな物語とも経験の普遍性とも異なる、より個人的な体験にフォーカスを当てた「展示」のあり方を探求する姿勢である。例えば滋賀の山中に位置する共同スタジオ、山中suplexで行われたドライブイン展覧会「類比の鏡」(2020)は、夜の屋外+人工的な光という、作品周辺のノイズを極力抑えた環境での鑑賞体験という点において、ホワイトキューブの仕組みを準用している。一方で「車」というユニット/複数人での移動を基本単位とし、椅子に座った低い目線と展示物との物理的な距離を展示プラン全体に取り入れることで、ホワイトキューブが無言のうちに前提とする理想的な身体や運動能力、それに伴う鑑賞とは異なるベクトルの体験を導入した展覧会でもあった。
もう一つの論点として、日本型アート・プロジェクト、あるいは地域アートと呼ばれる特定の地域で展開される展覧会/プログラムに対する、自身の仕事の立ち位置ついても話があった。地域展開を前提にした展覧会では、主催者や企画者側がアーティストに地域の歴史や資源に着目したサイトスペシフィックな作品を求める傾向にあるが、展示作品が場所と結びつくあまり、他の場所での展示が難しくなるケースは少なくない。こうした問題に対し、京都府福知山市で行われた展覧会「余の光」(2021)では、一回性の強いインスタレーションではなく「絵画」というメディウムを主軸に置くことで、地域の文脈を考慮しながら作品がその後も様々な文脈で編まれ、展示できる可能性を開くことを試みた。また国際芸術祭あいち2022では、出展作家のひとりであるユ・チェンタ氏を招き市民を巻き込んだパレードを行って、「性/生の解放」を肯定するアーティストの活動を街へ拡張させた。
展示室の外側で行われる展覧会の場合、キュレーションに強く求められるのは「なぜその場所か」という問いに対する態度である。こうしたタフさと批評性が求められる現場経験を重ねた現時点での考えとして、堤さんから「展覧会は上演である」という言葉があったのは非常に興味深かった。それは堤さんが影響を受けた人物のひとりとして挙げていた、劇作家・岸井大輔氏による「戯曲と上演」の定義へ繋がる。岸井氏によると、戯曲は自立しているため作品であるが、上演は様々な要素の重なりが質に左右する不確定なものであるために「作品」ではない、という。戯曲と上演をめぐるこの関係を展示行為に当てはめたとき、限られた期間だけ現れてまた消えていく「束の間性」や、見る人の体調や気分によって鑑賞体験が変化しうる不確定さを含む展覧会は、岸井氏が述べる「上演」のあり方に重なる。 この点について、質疑応答では研究員の方々を交えた活発な意見交換がなされた。
「展示」という今年度のテーマに関し、今回の堤さんの発表は、同時代の、かつ展示室の外での実践について非常に刺激的なお話を伺える機会だった。「美術」やその制度に対する見直しが進む今日において、西洋近代的な展示形式を部分的に取り入れながら、同時に批評的/懐疑的にまなざすキュレーションの方法論とその実践は、ひとつの希望に思われる。(渡辺)
【参考】
以下の論文を参考にした。
- 1.
- 松井勝正「ホワイトキューブの外側 ―ドナルド・ジャッド、リチャード・セラ、ロバート・スミッソンの都市への眼差し―」田中正之編『ニューヨーク ―錯乱する都市の夢と現実 〈西洋近代の都市と芸術7〉』竹林舎、2017年、pp.241-267
- 2.
- 本発表で言及されていたのは以下の4点。川口幸也編著『展示の政治学』水声社、2009年/岸井大輔(戯曲家・1970~)/W.J.T. Mitchell, “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture”, Journal of Visual Culture, 2002/ピオトル・ピオトロフスキー(美術史家・1952~2015)
- 3.
- 展覧会と上演との関係を扱った非常に興味深い展覧会として、「Re: play 1972/2015 ―「映像表現’72」展、再演」(東京国立近代美術館、2015年)
【連絡先】
きょうと視覚文化振興財団事務局
〒607-8154京都市山科区東野門口町13-1-329TEL:075-748-8232