
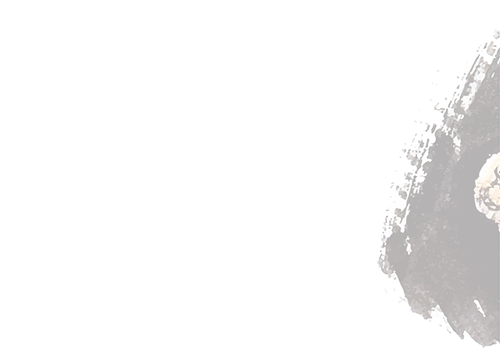
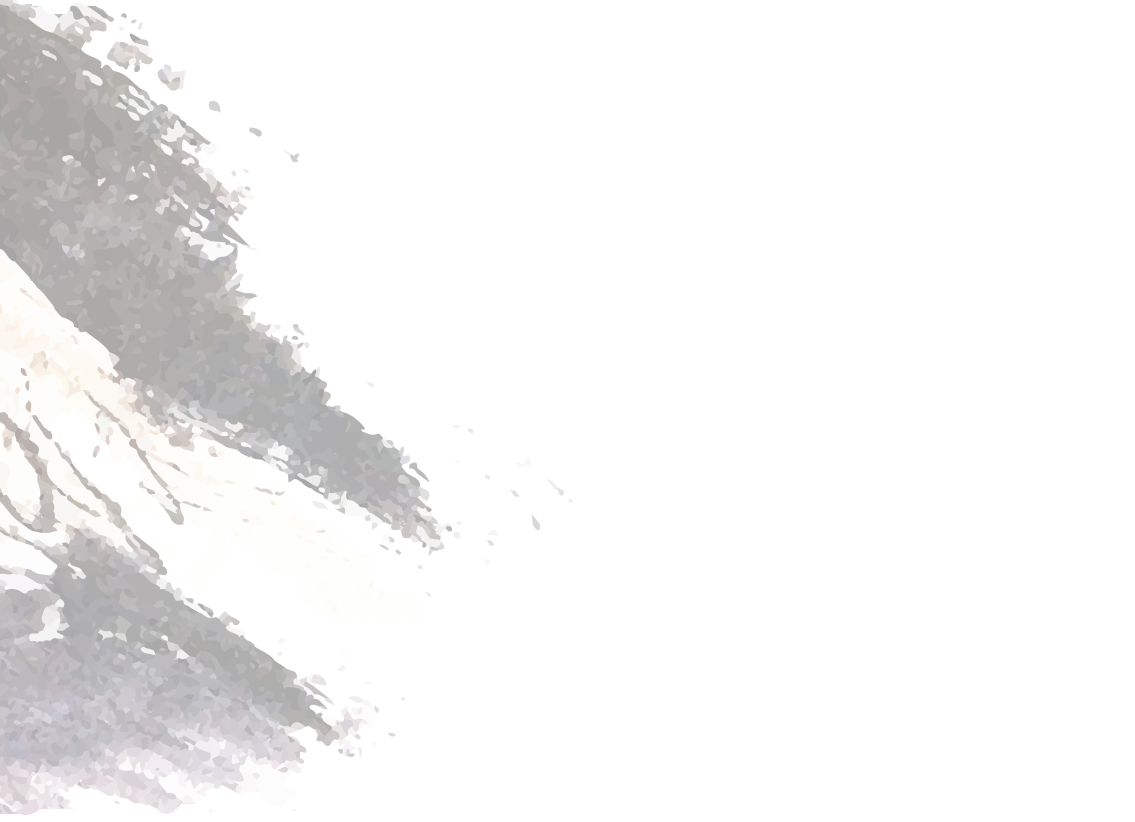
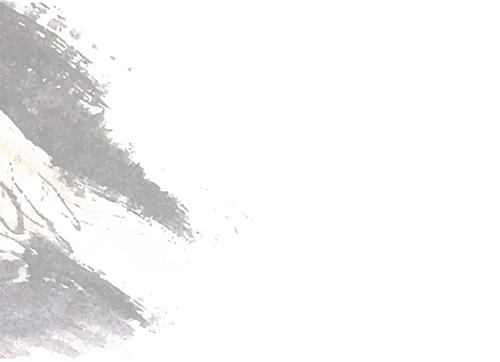



2022年度 第4回 視覚文化公開ワークショップが開催されました
2022年12月18日(日曜)午後2時から、同志社大学今出川校地良心館RY208教室で、第4回視覚文化公開ワークショップが、対面とZOOMのハイブリッドで行われました。会場には、今回の提題者である杉山卓史研究員はじめ、天野和夫、佐藤守弘、はがみちこ、渡辺亜由美研究員の面々が全員集合。財団からは、原田平作理事長、中谷伸生、岸文和理事、入江錫雄事務局長が参加しました。また、財団ホームページを通じて申し込まれた3名の方がZOOMで参加されました。今後も、奮ってご参加いただきますよう、お願いします。
今回のテーマは、「日常美学の可能性と限界」です。「日常美学」を「日常生活の美学」と同義とすると、この「美学」は、「お茶の美学」や「焼き物の美学」などと同じように、「日常生活」を美学的/感性論的に考察することなのですが、杉山さんの意図は、このようなことを考察することの意義について考えてみようというわけです。そのさい、「美学的/感性論的に考察する」ということが、何をすることであるかについて、すなわち、どのような問題を立て、どのような方法で、どのような結論を導くかについて、共通の認識を得ておくことが重要であることは言うまでもありません。しかし、もっと重要なことは、このような考察の対象になっている「日常生活」――美学的な問題が立てられる前提――が、そもそも何であるかについて、共通の理解を形成しておくことでしょう。杉山さんのご苦労も、その辺りをどのように整理するかにあったようにお見受けします。というのも、ワークショップの参加者は言うまでもなく、日常美学の研究者にとっても、「日常生活」という概念の外延と内包とが、必ずしも明晰判明ではなく、多様で曖昧であるように思われるからです。たしかに、共通のものがないわけではありません。「非芸術」「芸術の周縁」など、「芸術」とは呼ばれないモノやコト(ゲームやスポーツ)、あるいは、「高尚な文化」ではない「ローカルチャー」や「サブカルチャー」などもその候補でしょうか。しかし、「日常生活」を、何かの否定や対立/対比としてではなく、肯定的/自立的に定義することは、やはり相当に難しいように思われます。というか、そのこと自体、ハイデガーの「日常性(Alltäglichkeit)」――「人間が通常あるあり方」――を引き合いに出すまでもなく、哲学的な思索の対象であるからです。ともあれ、「日常美学」は、杉山さんの言うとおり、はが研究員の「資料」や佐藤研究員の「オルタナティヴ」と通底する問題意識に支えられています。この問題意識の延長線上には、「視覚文化」があるように思うのですが、それはさて措き、杉山さんご自身に「日常美学」の意義について報告をしてもらうことにしましょう。(K)
【内容】
0)はじめに
1)日常美学の類型と背景
2)事例紹介:貨幣の美学
3)日常美学は「新しい」のか?
4)日常美学から何を汲み取るべきか?
【概要】
今年度のこれまでのワークショップのキーワードを一つ挙げるなら、「日常」だったのではないでしょうか。たとえば、佐藤研究員が「オルタナティヴ」を主題とした第2 回では、この「オルタナティヴ」カルチャーを支えたDIY 的な「日常の」メディア(ガリ版+木版画〜DTP)が、「彫刻刀が刻む戦後日本──2 つの民衆版画運動」展(町田市立国際版画美術館)を参照しつつ紹介され、はが研究員が「資料」のあり方を問うた第3 回では、作品/展示に至る前の、いわば「舞台裏」としてのアーティストの「日常」の活動が紹介され、それぞれ活発な議論が展開されました。この流れを受けて、この第4 回では今世紀になって美学の一大潮流をなすに至った「日常美学(everyday aesthetics)」(「日常生活の美学(aesthetics of everyday life)」とも)を取り上げ、その多様なアプローチを類型化してその背景を探ります。しかし、日常美学は「新しい」アプローチなのか、美学が注目する以前から「日常」はさまざまな仕方で考察されてきたのではないか。このような反省に基づき、「日常」をどのように考察するか、そもそも「日常」を考察するとはどういうことか、参加者のみなさんとともに考えたいと思います。
【報告】
「日常美学」は、「美」や「芸術」といった美学の伝統的な研究対象「ではない」日常的なものを研究対象とする、美学の新しい研究分野です。その嚆矢は、ひとまず2005年にアンドリュー・ライトとジョナサン・L・スミスの共編によって出版された論文集『日常生活の美学』に求めることができるでしょう。その冒頭に置かれた「日常美学の本性」という導入的論文で、トム・レディは次のように述べています。「日常美学の分野は、芸術の美学、自然の美学、数学の美学など、既存の分野ではカバーされていない日常生活の領域をカバーする」。この論文集には、アーノルト・バーリアントやアレン・カールソンといった、英語圏で「環境美学」(環境問題への反省意識に端を発する、自然環境を美的に見ることに潜む諸問題を論じる美学の一分野)を牽引してきた論者たちが中心となって寄稿していることから、日常美学は環境美学の対象を「自然環境」から「日常環境」ないし「人間環境」に拡大・応用したものと見ることができるでしょう。こうした位置づけは、2年後の2007年に、ともに『日常美学』と題されたカーチャ・マンドーキと斎藤百合子の著作にも引き継がれます。ここで、この2007年の著者がともに非西洋圏出身の女性である、ということに注目しておいてよいでしょう。すなわち、日常美学は西洋の男性中心的な美学への異議申し立て、という側面をも持っているのです(こうした側面は、編者こそ男性ですが、2014年の刘悦笛とカーティス・L・カーターによる論文集『日常生活の美学——東洋と西洋』にも見られます)。
しかし、それだけで日常美学の特徴とすることはできません。2005年の論文集に所収のヴォルフガング・ヴェルシュ「美的に、さらには芸術としてさえ見られたスポーツ?」は、環境美学とは異なる背景を持っています。この論文は、もともと1998年にスロヴェニアのリュブリャーナで開催された第14回国際美学会議での(賛否両論を引き起こした)講演に由来していますが、それはヴェルシュ自身がかねてより(『感性の思考』1990年等において)提唱してきた「美学をその語源に即して『感性の学』と捉え直すこと」——今日ではしばしば「感性論的転回」と呼ばれます——の応用・実践でした。この提唱はドイツ語圏において広範な反響を呼び、ゴットフリート・ガブリエル『貨幣の感性論と修辞学』(2002年)やコンラート・パウル・リースマン『物の宇宙——日常的なものの感性論に向けて』(2010年)等の著作が続く他、2008年の第7回ドイツ美学会大会では「美学と日常経験」という統一テーマが掲げられました。
以上をまとめるなら、現在の日常美学は、アングロサクソン系の「環境美学」に由来するもの(そして、そこにはマイノリティからの異議申し立てという側面も付随します)と、ドイツ系の「感性論的転回」に由来するものとが混交している状況にある、と言えます。
しかし、ここで疑問がふと浮かびます。日常美学とは、はたして新しいものなのか?「日常美学」というラベルは新しいかもしれないが、それが貼られる以前から日常的なものの感性的側面に注目する学問的営みは存在していたのではないか?と。思いつくだけでも、鶴見俊輔が1960年代に提唱した「限界芸術論」(そこで鶴見は自身の先駆として柳田國男、柳宗悦、宮沢賢治などを挙げています)はこれに該当するでしょうし、上述のヴェルシュの「スポーツの美学」も、中井正一がすでに1930年代に論じています。あるいは、西洋美術における「風俗画」の誕生にも、ヒントがあるかもしれません。風俗画と既存の「格上」のジャンル(歴史画、宗教画)との対比は〈日常的なもの−非日常的なもの〉という対比と重なりますし、何よりgenre paintingという呼称自体が「既存のジャンルに収まらないもの」——いわば「その他もろもろ」——というニュアンスを持っているからです。
では、そのように必ずしも新しいものではないとしたら、日常美学から何を汲み取ることができるでしょうか?上述のレディは、「日常生活の美学を探求するより有益な方法は、美的用語を議論することによるものである」と述べています。「美的用語(aesthetic term)」とは、「美しい」「醜い」「優雅だ」など、対象への適用において感性をはたらかせることが求められる用語で、「美的性質」「美的概念」などとも呼ばれます(これについては、2021年度第4回ワークショップでも考察しました)。そのふるまいが、芸術などの「非日常的なもの」と「日常的なもの」においてどう異なるのかを考察することが日常美学にとって重要である、というのがレディの(そして斎藤も共有している)主張です。たしかに、これは一つの方向性と言えるでしょう。
もう一つ、私が気になっている(そして専門家間でも十分に議論されていないように見える)のは、マンドーキの著書の副題にある「散文学(prosaics)」という言葉です。すなわち、彼女は日常的なものと非日常的なものとの対比を「散文」と「韻文」との対比に重ねているのです。彼女は主に社会学における「日常」研究(シュッツ、ゴフマン等)を参照してその「散文学」を構築しようとしていますが、美学史を繙いても、散文と韻文の相違は何か(形式の問題なのか内容にもかかわるのか)、散文は芸術でありうるか、といった問題はしばしば論じられてきました(デュボス、ヘーゲル等)し、19世紀には「散文詩」というジャンルも誕生します。そう考えると、この「散文」への注目も、やはり新しくはないかもしれませんが、「日常」について感性的に考える一つの切り口と言えるかもしれません。
最後に私自身は、かつてガブリエルの『貨幣の感性論と修辞学』を批判的に検討する中で、「閾(threshold)」——ある事物は、それが一定量に達するまでは意識されないが、その量を超えると意識される、いわば「全か無かの法則」の、その一定量——という概念が日常的なものを感性的に考える上で有効なのではないかという提案をしましたが、これを彫琢していく必要もあるでしょう。
以上のような散漫な話題提供に対して、質疑応答においては当然のことながら「『日常』が何を指しているのか分かりづらい」「各論者における「日常」のレベルは異なり通約不可能ではないか」等のご指摘を多数いただきました。もっともなことです。ただ、やや開き直って言うならば、その「定義しがたさ」、前に風俗画の件でも言及した「その他もろもろ」感こそが日常美学の対象であり、それを念頭に置いたアプローチを考案する必要性を認識しました。また、従来専門家の狭いサークル内で完結しがちであったこの問題を、相対的に広い場に提示することにより、19世紀のアーツ・アンド・クラフツ運動、20世紀のカルチュラル・スタディーズ、さらには近年隆盛を見せている感情史研究との関係も、指摘していただきました。これこそ、この視覚文化ワークショップでこの日常美学という話題を扱うことで私が期待していたことでもあり、それは十分に果たされたように思います。
今回のテーマは、「日常美学の可能性と限界」です。「日常美学」を「日常生活の美学」と同義とすると、この「美学」は、「お茶の美学」や「焼き物の美学」などと同じように、「日常生活」を美学的/感性論的に考察することなのですが、杉山さんの意図は、このようなことを考察することの意義について考えてみようというわけです。そのさい、「美学的/感性論的に考察する」ということが、何をすることであるかについて、すなわち、どのような問題を立て、どのような方法で、どのような結論を導くかについて、共通の認識を得ておくことが重要であることは言うまでもありません。しかし、もっと重要なことは、このような考察の対象になっている「日常生活」――美学的な問題が立てられる前提――が、そもそも何であるかについて、共通の理解を形成しておくことでしょう。杉山さんのご苦労も、その辺りをどのように整理するかにあったようにお見受けします。というのも、ワークショップの参加者は言うまでもなく、日常美学の研究者にとっても、「日常生活」という概念の外延と内包とが、必ずしも明晰判明ではなく、多様で曖昧であるように思われるからです。たしかに、共通のものがないわけではありません。「非芸術」「芸術の周縁」など、「芸術」とは呼ばれないモノやコト(ゲームやスポーツ)、あるいは、「高尚な文化」ではない「ローカルチャー」や「サブカルチャー」などもその候補でしょうか。しかし、「日常生活」を、何かの否定や対立/対比としてではなく、肯定的/自立的に定義することは、やはり相当に難しいように思われます。というか、そのこと自体、ハイデガーの「日常性(Alltäglichkeit)」――「人間が通常あるあり方」――を引き合いに出すまでもなく、哲学的な思索の対象であるからです。ともあれ、「日常美学」は、杉山さんの言うとおり、はが研究員の「資料」や佐藤研究員の「オルタナティヴ」と通底する問題意識に支えられています。この問題意識の延長線上には、「視覚文化」があるように思うのですが、それはさて措き、杉山さんご自身に「日常美学」の意義について報告をしてもらうことにしましょう。(K)
日常美学の可能性と限界
京都大学大学院文学研究科准教授 杉山卓史
【内容】
0)はじめに
1)日常美学の類型と背景
2)事例紹介:貨幣の美学
3)日常美学は「新しい」のか?
4)日常美学から何を汲み取るべきか?
【概要】
今年度のこれまでのワークショップのキーワードを一つ挙げるなら、「日常」だったのではないでしょうか。たとえば、佐藤研究員が「オルタナティヴ」を主題とした第2 回では、この「オルタナティヴ」カルチャーを支えたDIY 的な「日常の」メディア(ガリ版+木版画〜DTP)が、「彫刻刀が刻む戦後日本──2 つの民衆版画運動」展(町田市立国際版画美術館)を参照しつつ紹介され、はが研究員が「資料」のあり方を問うた第3 回では、作品/展示に至る前の、いわば「舞台裏」としてのアーティストの「日常」の活動が紹介され、それぞれ活発な議論が展開されました。この流れを受けて、この第4 回では今世紀になって美学の一大潮流をなすに至った「日常美学(everyday aesthetics)」(「日常生活の美学(aesthetics of everyday life)」とも)を取り上げ、その多様なアプローチを類型化してその背景を探ります。しかし、日常美学は「新しい」アプローチなのか、美学が注目する以前から「日常」はさまざまな仕方で考察されてきたのではないか。このような反省に基づき、「日常」をどのように考察するか、そもそも「日常」を考察するとはどういうことか、参加者のみなさんとともに考えたいと思います。
【報告】
「日常美学」は、「美」や「芸術」といった美学の伝統的な研究対象「ではない」日常的なものを研究対象とする、美学の新しい研究分野です。その嚆矢は、ひとまず2005年にアンドリュー・ライトとジョナサン・L・スミスの共編によって出版された論文集『日常生活の美学』に求めることができるでしょう。その冒頭に置かれた「日常美学の本性」という導入的論文で、トム・レディは次のように述べています。「日常美学の分野は、芸術の美学、自然の美学、数学の美学など、既存の分野ではカバーされていない日常生活の領域をカバーする」。この論文集には、アーノルト・バーリアントやアレン・カールソンといった、英語圏で「環境美学」(環境問題への反省意識に端を発する、自然環境を美的に見ることに潜む諸問題を論じる美学の一分野)を牽引してきた論者たちが中心となって寄稿していることから、日常美学は環境美学の対象を「自然環境」から「日常環境」ないし「人間環境」に拡大・応用したものと見ることができるでしょう。こうした位置づけは、2年後の2007年に、ともに『日常美学』と題されたカーチャ・マンドーキと斎藤百合子の著作にも引き継がれます。ここで、この2007年の著者がともに非西洋圏出身の女性である、ということに注目しておいてよいでしょう。すなわち、日常美学は西洋の男性中心的な美学への異議申し立て、という側面をも持っているのです(こうした側面は、編者こそ男性ですが、2014年の刘悦笛とカーティス・L・カーターによる論文集『日常生活の美学——東洋と西洋』にも見られます)。
しかし、それだけで日常美学の特徴とすることはできません。2005年の論文集に所収のヴォルフガング・ヴェルシュ「美的に、さらには芸術としてさえ見られたスポーツ?」は、環境美学とは異なる背景を持っています。この論文は、もともと1998年にスロヴェニアのリュブリャーナで開催された第14回国際美学会議での(賛否両論を引き起こした)講演に由来していますが、それはヴェルシュ自身がかねてより(『感性の思考』1990年等において)提唱してきた「美学をその語源に即して『感性の学』と捉え直すこと」——今日ではしばしば「感性論的転回」と呼ばれます——の応用・実践でした。この提唱はドイツ語圏において広範な反響を呼び、ゴットフリート・ガブリエル『貨幣の感性論と修辞学』(2002年)やコンラート・パウル・リースマン『物の宇宙——日常的なものの感性論に向けて』(2010年)等の著作が続く他、2008年の第7回ドイツ美学会大会では「美学と日常経験」という統一テーマが掲げられました。
以上をまとめるなら、現在の日常美学は、アングロサクソン系の「環境美学」に由来するもの(そして、そこにはマイノリティからの異議申し立てという側面も付随します)と、ドイツ系の「感性論的転回」に由来するものとが混交している状況にある、と言えます。
しかし、ここで疑問がふと浮かびます。日常美学とは、はたして新しいものなのか?「日常美学」というラベルは新しいかもしれないが、それが貼られる以前から日常的なものの感性的側面に注目する学問的営みは存在していたのではないか?と。思いつくだけでも、鶴見俊輔が1960年代に提唱した「限界芸術論」(そこで鶴見は自身の先駆として柳田國男、柳宗悦、宮沢賢治などを挙げています)はこれに該当するでしょうし、上述のヴェルシュの「スポーツの美学」も、中井正一がすでに1930年代に論じています。あるいは、西洋美術における「風俗画」の誕生にも、ヒントがあるかもしれません。風俗画と既存の「格上」のジャンル(歴史画、宗教画)との対比は〈日常的なもの−非日常的なもの〉という対比と重なりますし、何よりgenre paintingという呼称自体が「既存のジャンルに収まらないもの」——いわば「その他もろもろ」——というニュアンスを持っているからです。
では、そのように必ずしも新しいものではないとしたら、日常美学から何を汲み取ることができるでしょうか?上述のレディは、「日常生活の美学を探求するより有益な方法は、美的用語を議論することによるものである」と述べています。「美的用語(aesthetic term)」とは、「美しい」「醜い」「優雅だ」など、対象への適用において感性をはたらかせることが求められる用語で、「美的性質」「美的概念」などとも呼ばれます(これについては、2021年度第4回ワークショップでも考察しました)。そのふるまいが、芸術などの「非日常的なもの」と「日常的なもの」においてどう異なるのかを考察することが日常美学にとって重要である、というのがレディの(そして斎藤も共有している)主張です。たしかに、これは一つの方向性と言えるでしょう。
もう一つ、私が気になっている(そして専門家間でも十分に議論されていないように見える)のは、マンドーキの著書の副題にある「散文学(prosaics)」という言葉です。すなわち、彼女は日常的なものと非日常的なものとの対比を「散文」と「韻文」との対比に重ねているのです。彼女は主に社会学における「日常」研究(シュッツ、ゴフマン等)を参照してその「散文学」を構築しようとしていますが、美学史を繙いても、散文と韻文の相違は何か(形式の問題なのか内容にもかかわるのか)、散文は芸術でありうるか、といった問題はしばしば論じられてきました(デュボス、ヘーゲル等)し、19世紀には「散文詩」というジャンルも誕生します。そう考えると、この「散文」への注目も、やはり新しくはないかもしれませんが、「日常」について感性的に考える一つの切り口と言えるかもしれません。
最後に私自身は、かつてガブリエルの『貨幣の感性論と修辞学』を批判的に検討する中で、「閾(threshold)」——ある事物は、それが一定量に達するまでは意識されないが、その量を超えると意識される、いわば「全か無かの法則」の、その一定量——という概念が日常的なものを感性的に考える上で有効なのではないかという提案をしましたが、これを彫琢していく必要もあるでしょう。
以上のような散漫な話題提供に対して、質疑応答においては当然のことながら「『日常』が何を指しているのか分かりづらい」「各論者における「日常」のレベルは異なり通約不可能ではないか」等のご指摘を多数いただきました。もっともなことです。ただ、やや開き直って言うならば、その「定義しがたさ」、前に風俗画の件でも言及した「その他もろもろ」感こそが日常美学の対象であり、それを念頭に置いたアプローチを考案する必要性を認識しました。また、従来専門家の狭いサークル内で完結しがちであったこの問題を、相対的に広い場に提示することにより、19世紀のアーツ・アンド・クラフツ運動、20世紀のカルチュラル・スタディーズ、さらには近年隆盛を見せている感情史研究との関係も、指摘していただきました。これこそ、この視覚文化ワークショップでこの日常美学という話題を扱うことで私が期待していたことでもあり、それは十分に果たされたように思います。

スクリーンに映されている書影は、左から、Yuriko Saito(2007), Everyday Aesthetics, Yuedi Liu and Curtis L. Carter (eds. 2014), Aesthetics of Everyday Life: East and West, Yuriko Saito (2022), Aesthetics of Care: Practice in Everyday Life. 左右のイメージが「日常美学」に使われるのは、何となく納得するところがありますが、中央の「Coca Cola」と記された壷は、会場で物議を醸しました。もっとも、このカバー・イメージは、「西洋と東洋の文化的対話を通じて日常生活の美学を再構築し、グローバルなパースペクティブから見た新しい形の日常生活の美学を構築しよう」とする編者・著者の決意を表しているようです。さて・・・
【連絡先】
きょうと視覚文化振興財団事務局
〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山51-35Tel / Fax:0774-45-5511